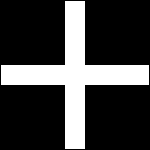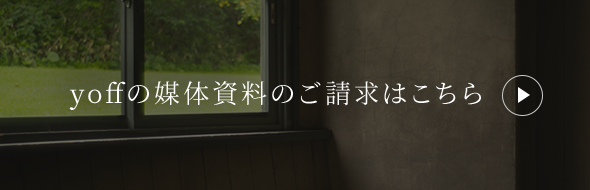花の都パリ、音楽の都ウィーン、など形容詞は、誰が名付けた。
Column|2024.11.25
Text_Kotaro Sakata
Photo_Kotaro Sakata
世の中が、今の様な『形容詞』で溢れだしたのは一体いつからだろうか? もちろん諸説あるが、起源は、人類史にまでは及ばない。
今から8000年前の四大文明の発祥の頃はまだ、大げさな形容詞は、なかったようである。世界最古の貨幣を言われる銀貨として、紀元前4300年頃から紀元前1530年頃まで古代メソポタミアにおいて使われた『ハル』が生まれて、モノと通貨が交換できるようになって、『このモノは、誰が作った』という言葉が残っている。つまり、ブランド価値を高めるためというより、モノを少しでも高値で売りたいというところに起源がありそうだ。そこから月日が流れ、大航海時代になると物流が発達し、地域と産地が密接に関わり合いを持ち始め、貿易で富を築く頃には、今でいう『盛る』とか『映え』の様な形容詞がやたらと多くなってくる。戦国時代以前から日本では、伴天連と言われる布教者からの『輸入モノ』と国内の産地とで分けられた。そして、明治維新を迎え、海外に文明開化の情報を求めるようになると、16世紀から使われて来た『南蛮渡来モノ』が、舶来品となり、外国の地に形容詞がつくこととなる。
代表的なものが、『花の都』と呼ばれた巴里(パリ)である。日本から見て、パリは、渋沢栄一に代表される使節団が巴里万博を見たことから形容されたようだ。しかし、『花の都』とは、ヨーロッパでは、フィレンツェの事であり、パリは花に溢れているわけではなく、英国で起きた産業革命が、フランスに伝播し、花開いたことから、日本ではあこがれの地として、『花の都、巴里』と形容された。方や、パリでは、日本文化が輸入されるようになり、浮世絵に代表される色鮮やかな色彩を放つ『日イヅル國』(聖徳太子曰く)として、ゴッホなどは、日差しが燦燦と降り注ぐあこがれの地こそが日本であり、日本の日差しを求め、曇ったパリを出て、アルルに拠点を置くこととなる。彼は、弟のテオを通じて多くの印象派の画家達に『ここには、色鮮やかな日本の光がある』と記している。さかのぼると、マルコ・ポーロは『東方見聞録』に『黄金の国ジパング』と形容しているので、13世紀から日本は憧れの地であったことだろう。
今では、形容詞が日進月歩で使い捨てにされているが、ネット社会になる前のバブル期を思いだせば、携帯すらない時代に、固定電話で伝えあっていたわけですので、隔世の感がある。
そこからは、皆さんが御存じの通り広告でのキャッチコピーに代表される、本質とはかけ離れている形容詞が躍るわけである。となると、今日生まれた形容詞に彩られたブランドは、皮肉なことに明日には、別の形容詞がつくという『言葉の使い捨て文化』が現世界の形容詞なのだろう。
Who coined names like “City of Flowers” for Paris or “City of Music” for Vienna?
When did the world begin to overflow with such descriptions? While theories vary, their origin doesn’t trace back to ancient history.
Around 8,000 years ago, during the rise of the four great civilizations, grand descriptors were absent. As one of the earliest known forms of currency, the Hal silver coins from ancient Mesopotamia (circa 4300–1530 BCE) enabled trade, with descriptions of provenance and the like aiming more at higher prices than brand value. By the Age of Exploration, as trade and logistics connected regions, descriptors similar to today’s “rich” or “glorious” emerged. In Japan, even before the Warring States period, goods were classified as missionary imports or local. With the Meiji Restoration, “Namban” imports, dating from the 16th century, became “foreign goods,” and foreign lands gained poetic descriptors.
Paris, labeled as the “City of Flowers,” gained this title in Japan after a delegation headed by Eiichi Shibusawa attended the Paris Exposition. Yet, in Europe, Florence holds this title; Paris’s association came from Britain’s Industrial Revolution blooming in France. Meanwhile, Paris started importing Japanese culture, viewing Japan, with its vivid ukiyo-e colors, as the “Land of the Rising Sun” (a term from Prince Shōtoku). For artists like Van Gogh, Japan represented a land bathed in warm sunlight, inspiring him to leave gray Paris for sunny Arles. Through his brother Theo, he wrote to many Impressionist painters that “Here is the vibrant light of Japan.” Looking back, Marco Polo called Japan the “Golden Country Zipangu” in The Travels of Marco Polo, making Japan a land of allure as far back as the 13th century.
Today, adjectives are quickly used and discarded, but recalling the pre-Internet Bubble Era when messages traveled only by landlines, it feels like another world.
From there, as you know, advertising slogans became full of adjectives often having little to do with the products themselves. Today’s brands wear adjectives like fast fashion, and ironically “throwaway culture of words” is an apt description of our world.

本当の『花の都』フィレンツェの赤い屋根群

『音楽の都』ウィーンの中心的シンボル、シュテファン大聖堂の洗浄前の姿